隠遁Chemistと愛(AI)の交換日記
HSPiPを開発しているAbbott先生と山本(LLC: pirika.com社CEO)は大阪大学の松林先生を訪問した。
横浜からNetで検索すると新大阪から大阪に出て梅田から蛍池でモノレールに乗り換えて行けという。素直にその夜の宿は梅田に取った。
新大阪に着いて梅田への行き方を見ていると、千里中央からのモノレールがある。?????
AIよ。僕を田舎もんと、馬鹿にしているのか?
まー、馬鹿にされても仕方がないが。
その宿のWiFiが最低で全然繋がらなかったのがオマケで。でももう梅田に行くことは無いだろうから忘れよう。
松林先生はMD関連の先生だ。Abbott先生が共同研究しているYork大学の清水先生が松林先生のところと関係がある。その縁で今回の訪問になった。
せっかくだから、学生に30分程度HSPの基礎を話してくれっていうので準備をした。
HSPとMDを繋げるような話を作っておいた。
そしたら、30分と言わずにフルに話してくれっていう事になった。AIに負けないような研究の仕方って教えておいて、そのやり方をAIに教育しているんだから矛盾しているよな。でも、聞き逃したり、忘れちゃったりした時は、学生よ。AIに聞いてくれ。
ハンセン溶解度パラメータの基礎
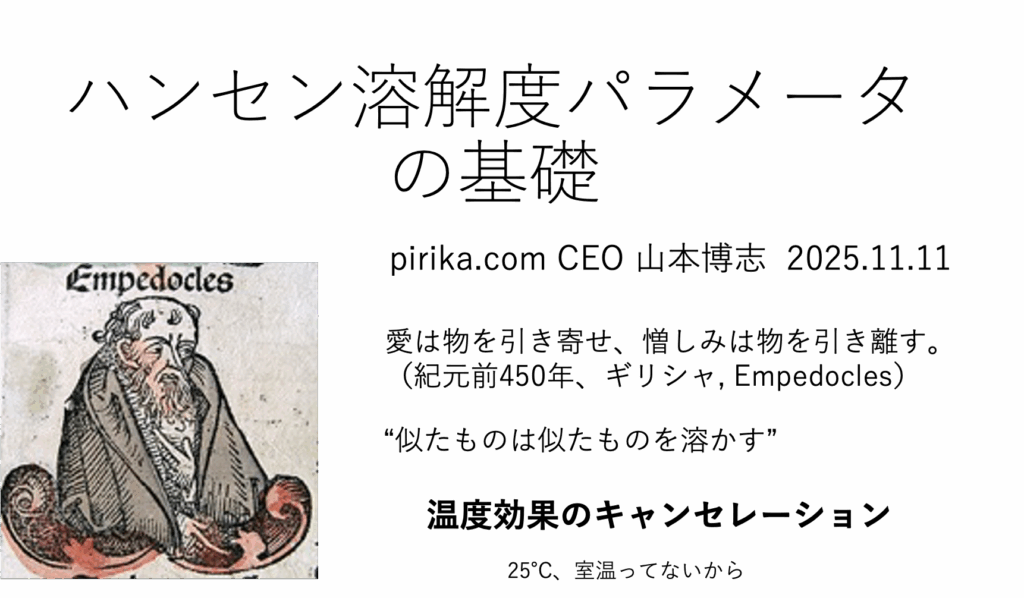
ギリシャ, Empedocles (紀元前450年)は、「愛は物を引き寄せ、憎しみは物を引き離す」と言ったとか。(あまりよくわかっていない人らしいが、火山に身を投げて自殺したとか。その時に靴を綺麗に揃えていたとかも言われている。)
ページの頭に、温度効果のキャンセレーションとか書いているけど、それは後半の話なので、ブログは分かれる。Empedocles の愛の形は強く引き寄せるような愛だ。ハンセン先生のような包み込む愛ではない。
溶解度パラメータとは?
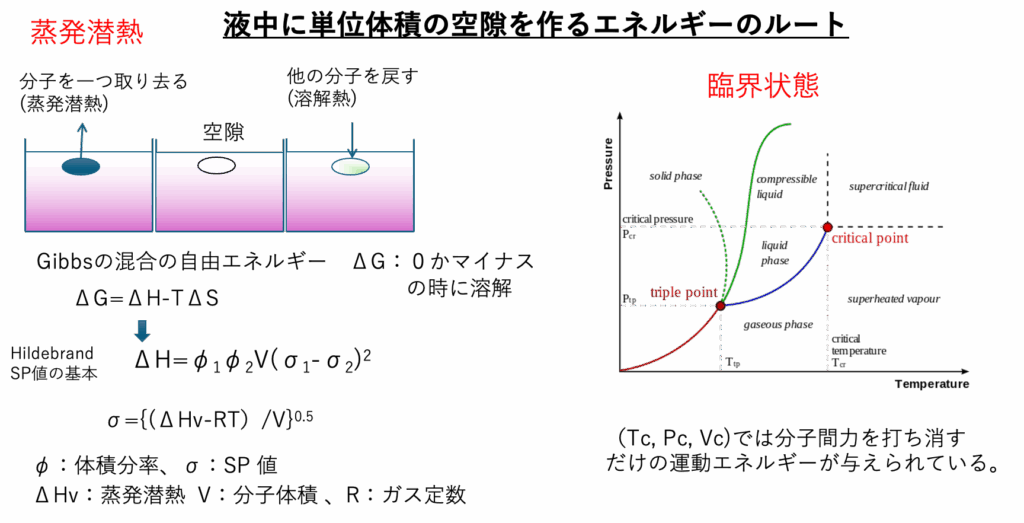
液体から分子を一つ取り出し、空隙を作る。その空隙に他の分子を戻す。そのエネルギー差を使うと
Gibbsの混合の自由エネルギー ΔG=ΔH-TΔS
ΔH:エンタルピー項が得られる。蒸発のエネルギーは25℃での蒸発潜熱と他の分子を戻す時の溶解熱で計算できるが、通常は溶解熱は大きく無い(今苦しんでいる酸塩基相互作用は無視)ので無視する。
HildebrandはこのΔHを
ΔH=φ1φ2V(σ1-σ2)2
と書いた。この時に始めて溶解度パラメータσが生まれた。
HildebrandのSP値は
σ={(ΔHv-RT)/V}0.5
と書ける。
分子集合体である液体を完全にぶち壊すにはどのくらいのエネルギーが必要なのだろうか? 臨界点(臨界温度Tc, 臨界圧力Pc, 臨界圧力Vc)では分子間力を打ち消すだけの運動エネルギーが与えられていると考えて良い。
ハンセンの溶解度パラメータとは?
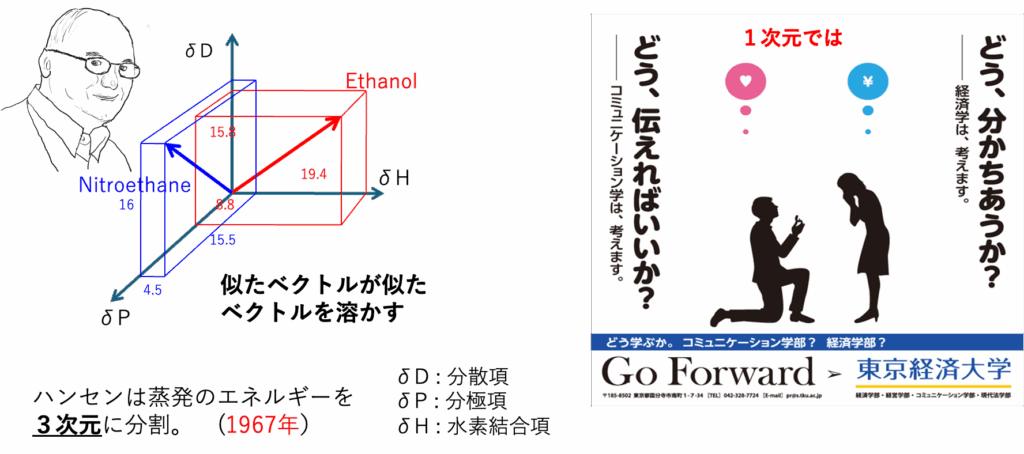
Hansen先生は1967年に、この蒸発のエネルギーを3次元に分割した。δD : 分散項 δP : 分極項 δH : 水素結合項の3つだ。そして、似たベクトルが似たベクトルを溶かすという原理になる。ある大学のポスターにあるように、1次元で考えるとミスマッチが起こる。
初期の実験装置
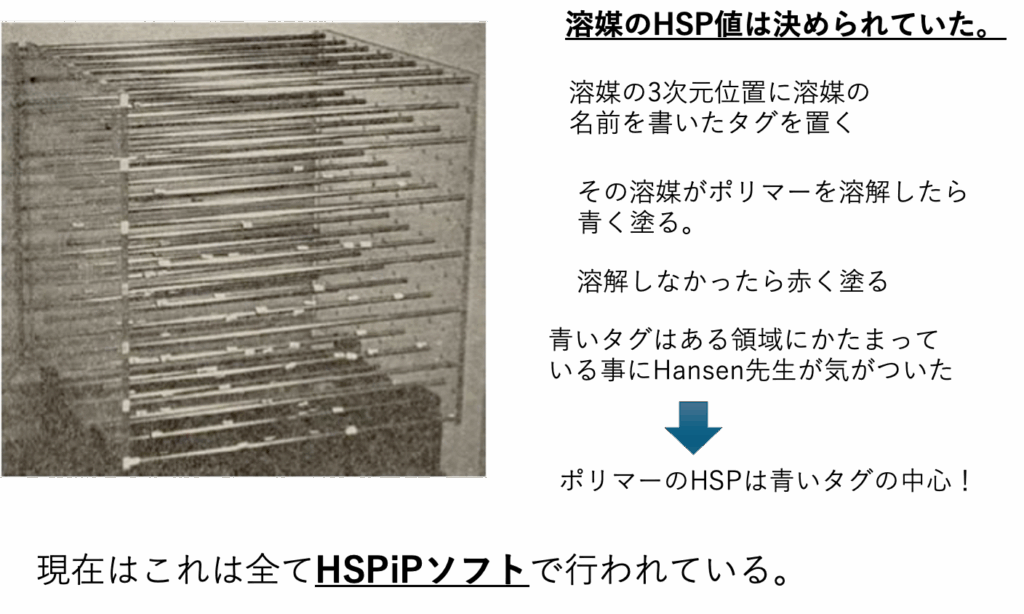
溶媒のHSP値は決められていた。溶媒の3次元位置に溶媒の名前を書いたタグを置く。
その溶媒がポリマーを溶解したら青く塗る。溶解しなかったら赤く塗る。青いタグはある領域にかたまっている事にHansen先生が気がついた。ポリマーのHSPは青いタグの中心と求まる。現在はこれは全てHSPiPソフトで行われている。
溶質(ポリマー)のHansenの溶解度パラメーター
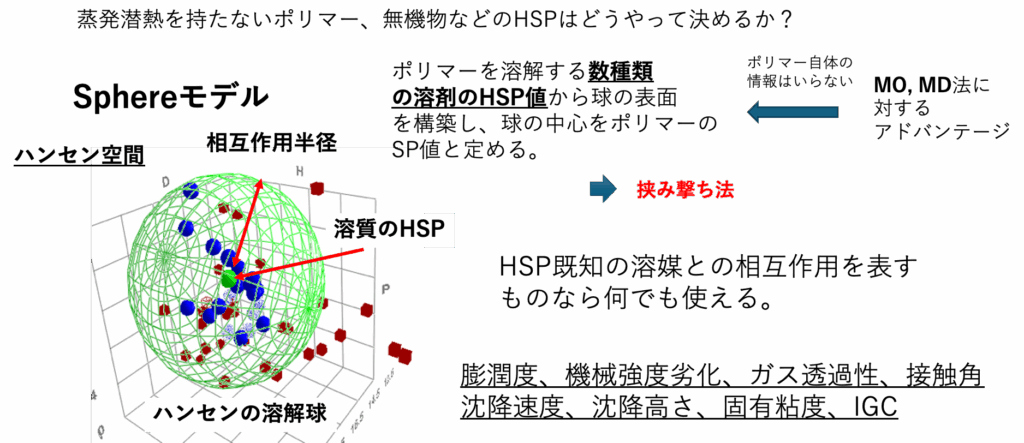
蒸発潜熱を持たないポリマー、無機物などのHSPはどうやって決めるか?という問題である。MO, MD法に対する大きなアドバンテージであるが、活性炭や複合材など構造がはっきりしなくてもHSPを決定できる。対象物自体の情報はいらない。ポリマーを溶解(分散)する数種類の溶剤のHSP値から球の表面を構築し、球の中心をポリマーのSP値と定める。球の表面を構築するには、HSPが既知の溶媒との良溶媒、貧溶媒がが決まれば良い。何を持って良溶媒、貧溶媒と呼ぶかは研究者次第である。
膨潤度、機械強度劣化、ガス透過性、接触角、沈降速度、沈降高さ、固有粘度、IGCなんでも良い。同じポリマー、無機物であっても研究者の良し悪しの判断でHSPの値は異なる。自分の判断を持たない研究者は生きづらい事になるかもしれない。
重要な言葉は覚えておこう。良溶媒がなるべくハンセンの溶解球(緑の大きなメッシュ)の内側に入り、貧溶媒が溶解球の外側に来るような、溶解球の中心と溶解球の半径(相互作用半径)を求めるのがSphere法だ。自分が作った理論のように書いている日本の大学の先生がいるが、これはHansen先生が1967年に発表した方法だ。それをソフトウエアー化しているのは、Abbott先生と私(pirika.com社のCEO山本)だ。バッタモンのソフトを使うのは勝手だが、それをHSPとは呼んでほしくない。
同じ事をやってみよう!
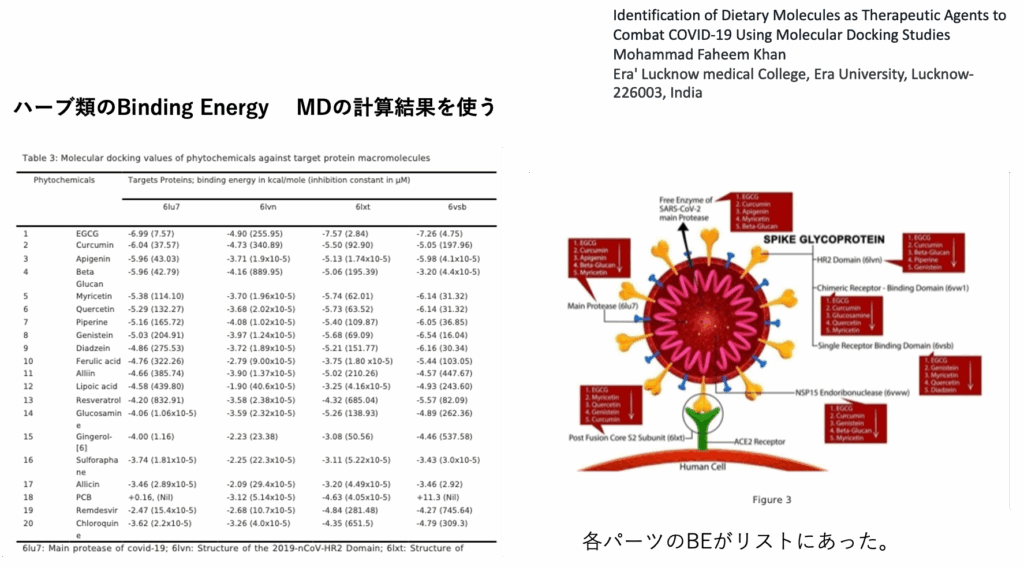
今回参加の大阪大学の学生はMDは専門でもHSPは触ったことがない事も多いだろう。
そこで、MDとHSPを繋げられるような例題として、コロナウイルスとハーブのBinding Energy(BE)を利用する事にした。
インドの大学が、ハーブ類とコロナウイルスの様々なパーツのBEをMDで計算した結果を発表していた。(講義の際にその計算条件を質問された。それは僕に聞いてはいけない。その辺りはほぼ素人なのだから)
先ほど、「何を持って良溶媒、貧溶媒と呼ぶかは研究者次第である」と書いた。HSPが既知のハーブのどれを良溶媒、貧溶媒と呼ぶかを決めればHSPを決めることができる。
コロナウイルスのパーツのHSP
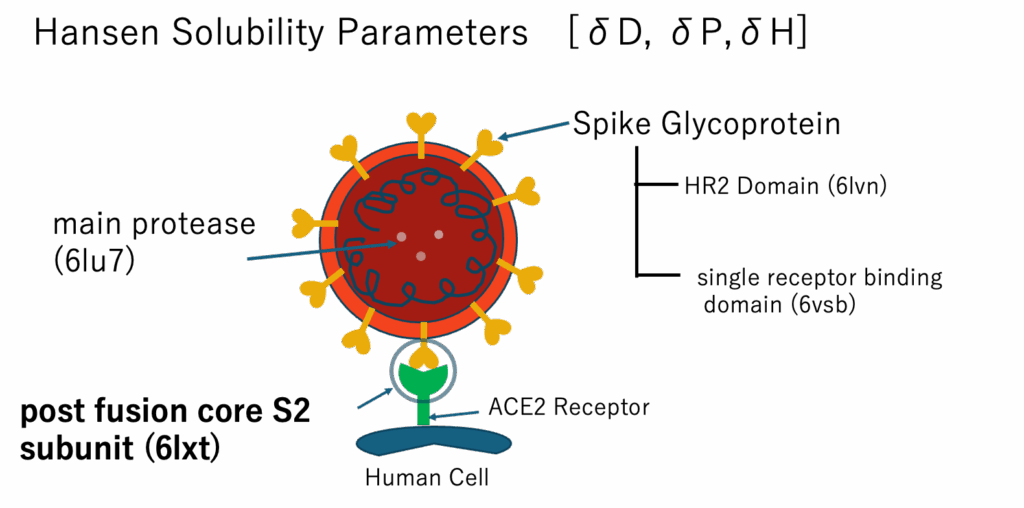
いろいろなパーツがあるけど人間の細胞にくっつく6lxtのHSPを求めてみよう。
ハーブのHSPから6lxtのHSPを求める
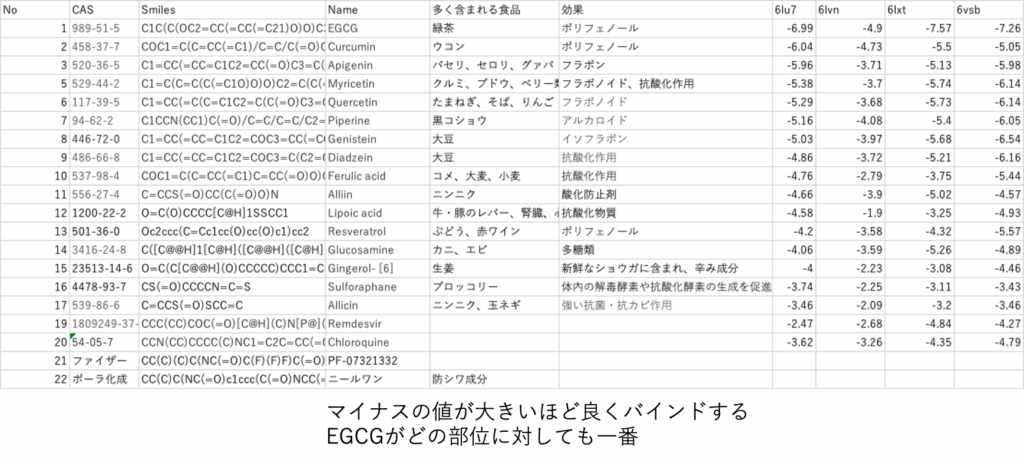
HSPの重要な機能の一つに、分子のSMILES構造式からHSPを推算するYMBという物性推算式がある。私が作成し、HSPの公式な物性推算方法だ。
ハーブのSmilesの構造式を用意しておけば計算でHSPが手に入る。
このYMB推算値を逆解析して官能基のHSPを決定したとか発表している恥知らずな日本の大学がある。ソフトウエアーの計算値をクラッキングするのを学位論文にしている。すごい大学があるもんだ。どの大学だか探してみよう。
Binding EnergyとHSP距離が高い相関になるようにHSPの中心を求める
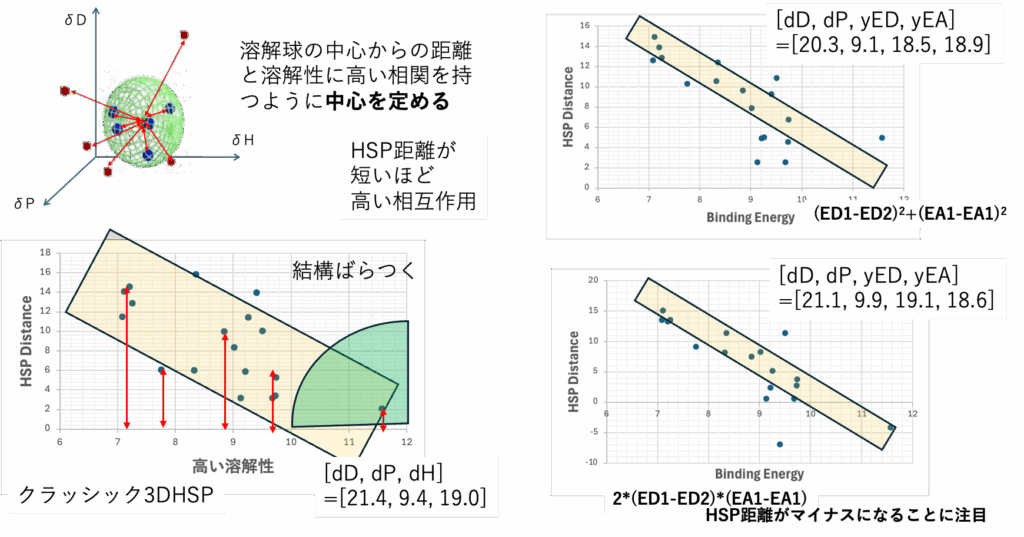
先ほど、良溶媒がハンセン溶解球の内側、貧溶媒が外側になるように中心と半径を求めると書いた。他に山本が作ったData Pointsという解析方法がHSPiPに搭載されている。これは定性的解析ではなく、HSP距離と溶解性に高い相関があるように溶解球の中心だけを求める。定量的な解析方法だ。このやり方では、良し悪しの堺が無いので溶解球の堺(球の表面)はなくなってしまう。半径が6ぐらいとして書いた方がわかりやすいかもしれない。
クラッシックの3次元(3D)のHSPで6lxtのHSPを求めると、[21.4, 9.4, 19.9]となる。結果を左下に示してあるが、かなり大きくばらついている。HSP距離が短いと(ベクトルが似ていると)BEが大きいとは言えないのがわかる。
この問題に対して、山本はHSP50周年記念講演会以来、新たな指標づくりに取り組んできた。やり方や結果を公開すると、えげつない研究者にクラッキングされるので、限定ユーザーにしか示してはいない。(今回HSPiPのソースコードを手に入れたので、限定ユーザーに特殊な機能を提供することができるようになった)
このクラッシック3D-HSPでHSP距離とBEに相関が出ないのは、dH(水素結合項)に酸塩基が入っていないためだ。先ほど、溶液から1分子取り出して空隙を作りそこに他の分子を戻すと説明した。その時の溶解熱は小さいので無視すると言った。
カルボン酸の溶液から1分子取り出して空隙を作りそこにアミンを戻したらどうだろう?
大きな中和熱が発生する。
第2周期のフッ素までならブレンステッド酸塩基で考えていても良いのだが、それ以上ではルイスの酸塩基で考えなくてはならない。山本が次世代HSP2で定義したED(Electron Donor) EA(Electron Acceptor)を使って解析をしてみると飛躍的に高い相関が得られることが右の二つの図からわかる。
dHの分割項を、Beerbower式で扱う。
2*(ED1-ED2)*(EA1-EA1)
この時にはHSP距離が負になることがあるのは非常に重要な点だ。覚えておくように学生を指導してくれ。
軸を選べるのがデジタルの良いところ
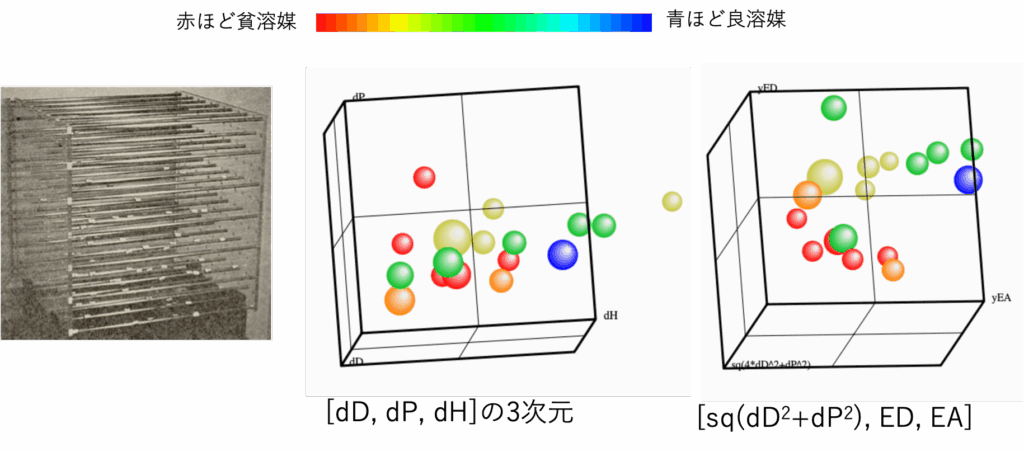
ハンセン先生が使っていた装置と違って、デジタルは自由に軸を選んで表示することができる。
AIにはプルダウンメニューを選んで表示を変えることはできないだろう。
暇な学生に頼んでやってもらおう。
クラッシックの3D-HSPとED,EAを使った時にどう違うか上の図を参照に自分でやってみよう。
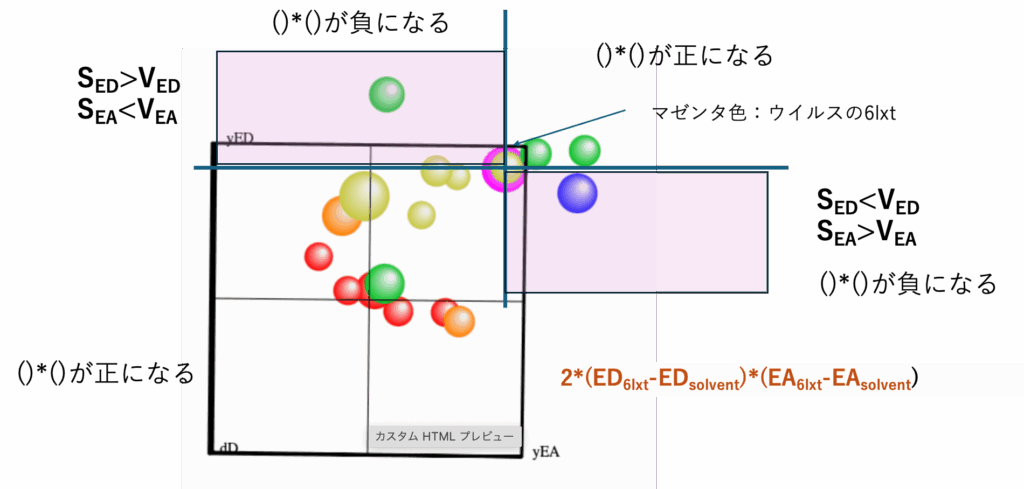
マゼンタ色がウイルスのHSPになる。
2*(ED6lxt-EDsolvent)*(EA6lxt-EAsolvent)
この式が負になるのは左上と右下の領域であることは容易にわかるだろう。
そこにある時には、距離の式の水素結合項分はマイナスになる。(dD, dPの値次第では距離の式計算値自体がマイナスになる。)
そこにある溶媒が3次元的に距離が長く見えても、実際には短くなる。右上と左下は逆に見かけよりは距離が長くなる。ただしこの負になる値は大きく離れた時にはとても大きくなってしまう。でも大きく離れるとということはEuclid距離はとても長くなる。
(ED6lxt-EDsolvent)2 + (EA6lxt-EAsolvent)2
この2つの式をどこで折り合わせるか? 難しいポイントである。
コロナの薬とされるもののHSPを勝手研究しよう
こうしたことがわかってくると、コロナの薬と言われているものを勝手にHSP計算してしまうことができる。
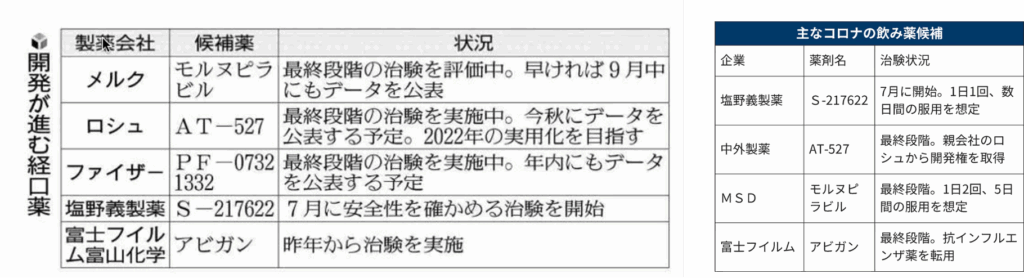
ネットとかに構造が出るたびに勝手に計算してしまうことができる。
シオノギのS-217622
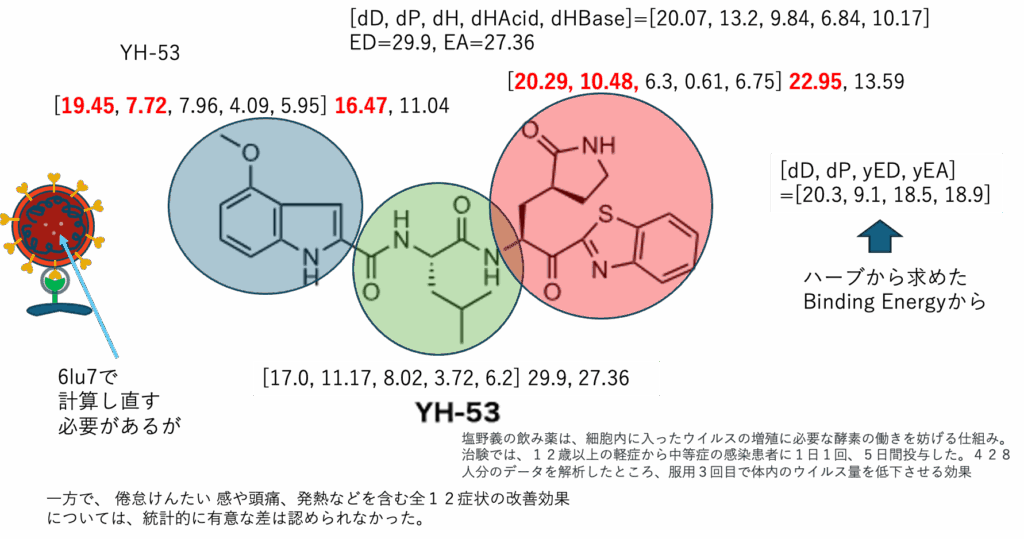
ハーブからMDで計算されたBEから6lxtのHSPを勝手に計算してしまう。
そこで求まったHSPと薬のパーツのHSPをSmilesの構造式から計算してどう関与しているのか考えるのは純粋に楽しい。
楽しくなければ勝手研究にはならない。AIはいくら計算しても楽しいとは思わない。
なんでファイザーは合剤なのか勝手に考える
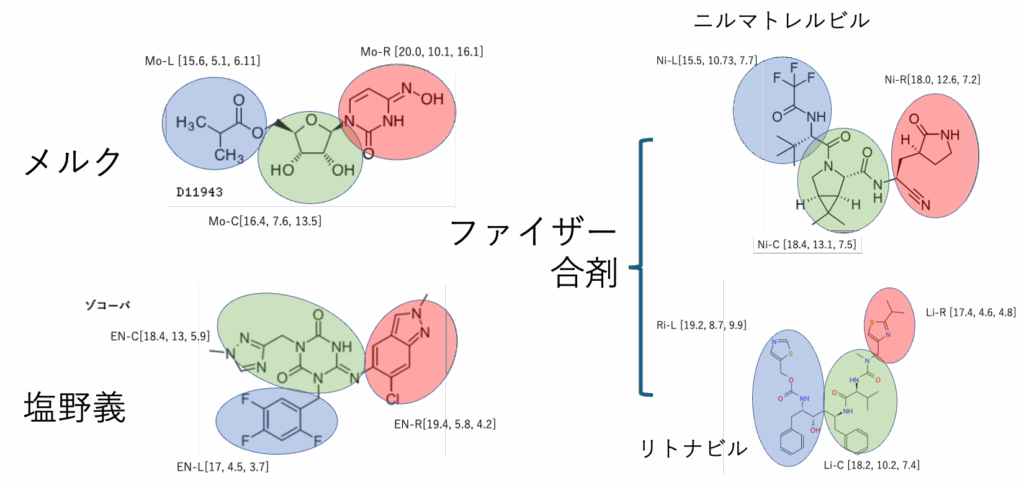
勝手研究の醍醐味。ウイルスをトラップするマスクを考えてみよう。
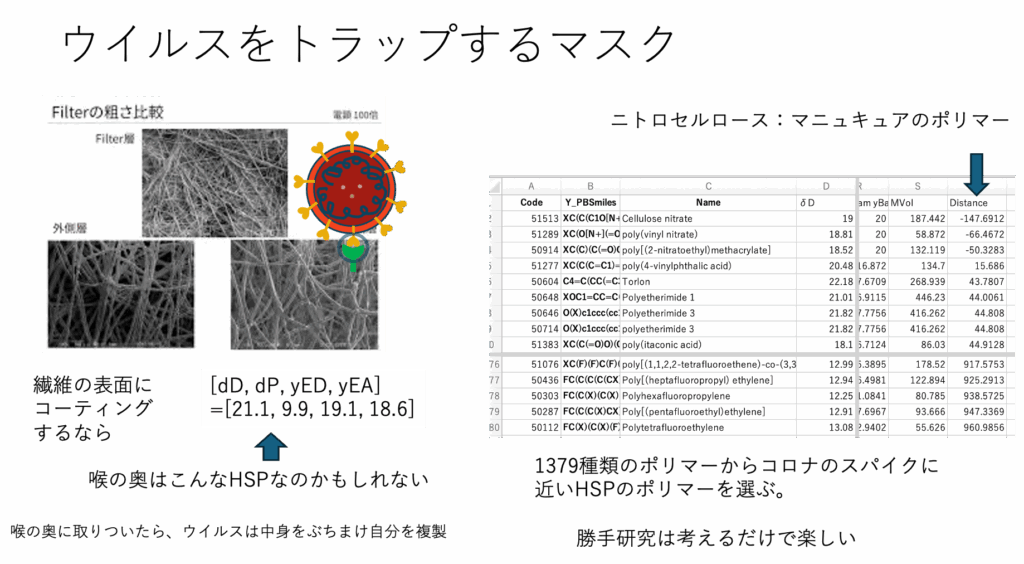
不織布のマスクの上にどんなものを塗ったらもっと効果があるか?
ウイルスは喉の奥に取り付いて自分の中身をぶちまけて複製を図る。
ウイルスが取り付く表面のHSPと同じHSPを持つポリマーをコーティングしたらどうなるか?
簡単だ。HSPiPに搭載のポリマーSmilesから1379種類のポリマーを計算してソートすればいい。(ただしポリマー推算のY-PB機能にはyED, yEA推算機能は搭載されていない)
僕は実験して特許を取ることはできないけど、勝手研究して誰も特許取れないように公知化してしまうことはできる。
Abbott先生と関西に向かう新幹線の中で
僕も先生も、ワーカホリックだ。高市なんて目じゃ無い。
大学で話す内容は事前に作っていたけど、講義前に既に内容が変わってしまった。
ED(Electron Donor)やEA(Electron Acceptor)はHSPの理論に載せるのは大変だ。いまだに僕は苦しんでいる。
今回、Abbott先生の来日に合わせて、EA,EDではなくdHacid, dHbaseの山本バージョンの分割を目玉にしようとしている。(先生のちゃぶ台返しで搭載はなくなった。ごめん)
次期バージョン dH分割の変更
次世代で無いので注意してほしい。次世代はいつ出るかわからない
次期バージョンは早ければ来年には出るかもしれない。次期バージョンに新しいdH分割は載らない。
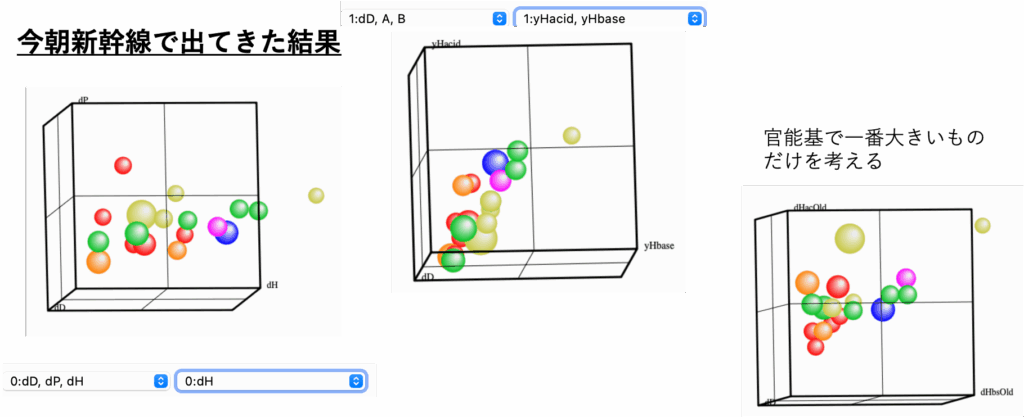
新幹線の中でいろいろ計算して資料を改訂した。
デジタルのいいとこだけど、これまでの結果を原子団に割り振ると、ED, EAの一番大きい原子団だけを考えるとか、dHAc/dHbsの一番大きい官能基だけを考えることができる。
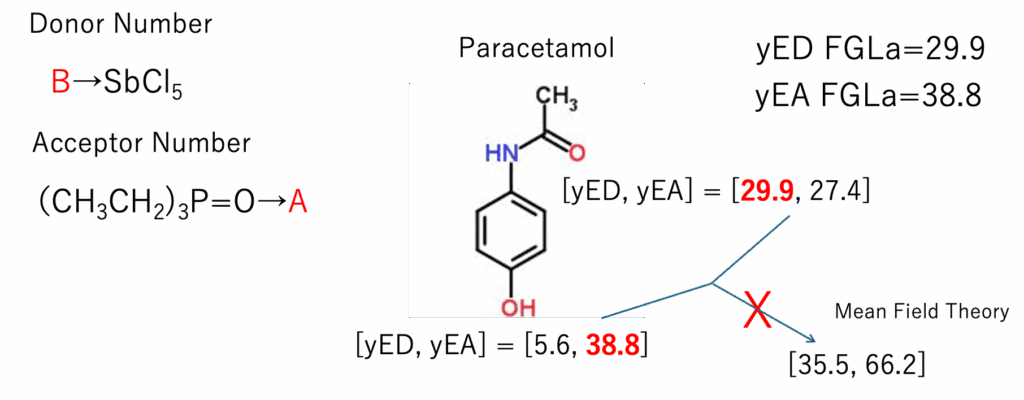
複数の官能基を持つ分子で考えるとわかりやすい。
ED, EAの一番大きなものだけが働いているという考え方を導入する。
Bonding Energyは平均場近似ではない
HSPの基本的な考え方は平均場近似になる。
でも、一番大きい値だけが働いていると考えた方が良い場合もたくさんある。
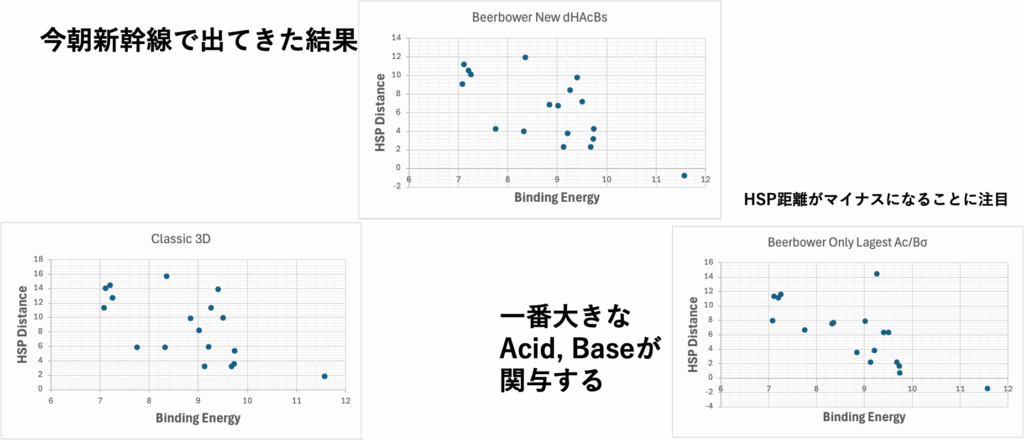
どう見ても平均場近似で見ていたら何が起きているかはわからない。
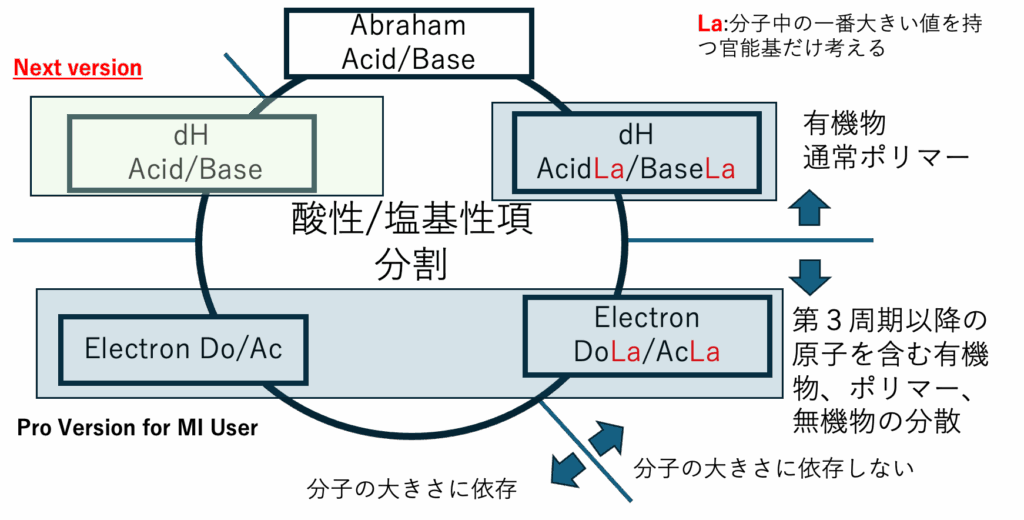
次世代のHSP2ではよく使う分割法チャートだ。
Abbott先生といろいろ半分喧嘩腰で議論しているが、次のバージョンでは新しいdH分割が搭載されるだけになりそうだ。ごめん。のらない。
結局、Abbott先生はLewisの酸塩基をY-MBでもY-PBでも拒否しているので、HSPiPには載らない。
ただ、HSPiPのソースコードは全部手に入れたので、僕の解釈での新世代の計算については、CLI Proとして別途提供することが可能になった。
ソフトをクラッキングしようという大学には提供しない。日本の素材産業を支え打ち勝っていかなくてはならないところとはwin-winの関係を築いていこうと思うかもしれない。
松林先生の話では、HSPでもっとどうにかしたい会社は関西にはいっぱいあるという。
先生のところに相談に来る会社は皆、HSPiPを持っていてその結果とMDの結果をどうやって統合化していくか?が問題になっているらしい。
その時には距離をマイナスにする強い力を導入する必要がある。
今はコンサル契約している会社にしか提供していない次世代HSP2をどう載せこんでいくか。
どこかの大学が酔狂にも僕が論文に自由にアクセスできるようにタイトルや研究者番号を与えてくれれば考えるかもしれない。
もうめんどくさくなってそんなもの要らなくなるかもしれない。
まー、ここ数年が勝負かな。
温度のキャンセルは別のブログで。

「AIよ。Abbott先生とのどさ回り。大阪の地理はもっとちゃんと教えてくれ。大阪大学でフルに講義した内容を学生に詳しく教えてくれ。」への1件のフィードバック
コメントは受け付けていません。