隠遁Chemistと愛(AI)の交換日記
情報化学系非線形解析ソフト、MIRAI(Multiple Index Regression for AI)はデータ数が少ない、識別子が多い、非線形性があるケースに使う解析ツールだ。pirika.com社の山本CEOによって開発が進められている。詳しくはこちらのページを参照してくれ。
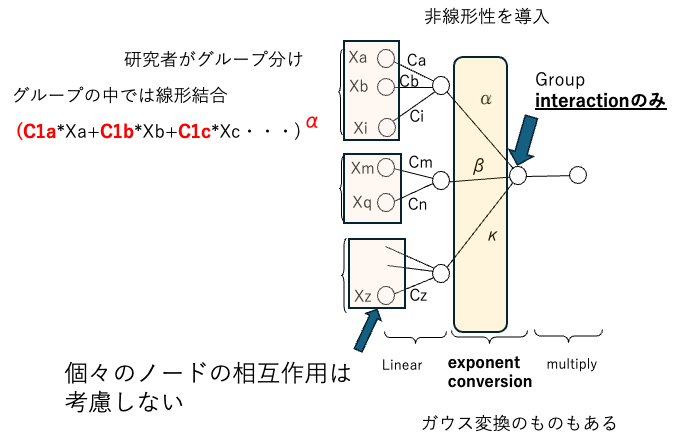
グループ分けがみそになる
例えば、ガラスの物性推算の時にアルカリ金属、アルカリ土類、、、、
例えば、ゴムの処方設計の時にゴムの種類、カーボンブラックの種類、受酸剤の種類、、、
そしてグループの中では線形結合で表現し、それをまとめて指数関数やガウス関数で非線形変換をかける。非線形性はグループ間だけ考える。
むかし、再構築学習法を使ったニューラルネットワーク(NN)をずっと使ってきた流れで私が開発した方法だ。ネットワークを研究者が自分で簡略化させて過学習を抑える方法が処方設計などでとても有効だ。
頭につくHSPはハンセンの溶解度パラメータのHSPだ。
様々な熱物性を、分散項、分極項、水素結合項などに分割する。
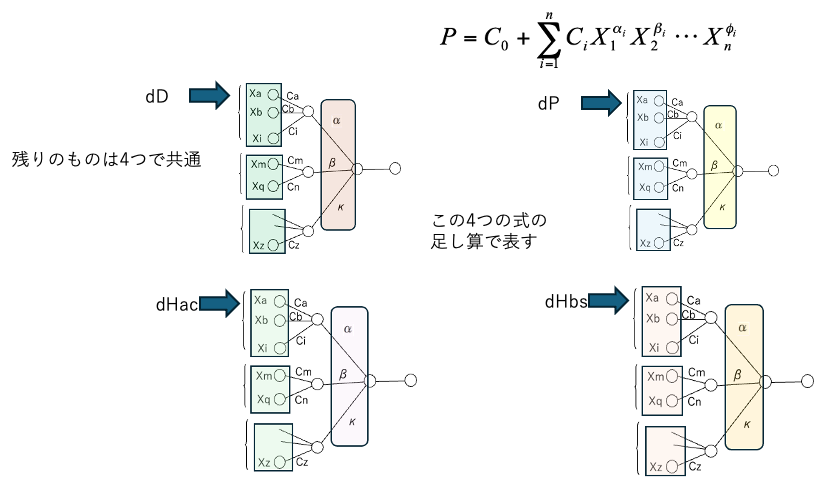
簡単に言ってしまえば、熱物性値をMIRAIのNN4つの足し算で表すことができると仮定して係数を遺伝的アルゴリズム法(GA法)を使って決めてしまう方法だ。このHSP-MIRAI法もpirika.com社山本CEOが開発したソフトだ。
HSP-MIRAI法による溶媒の表面張力分割式
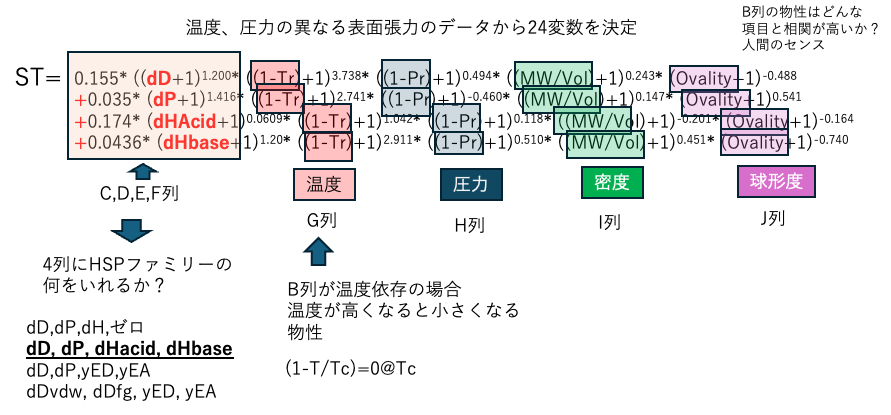
ある温度、圧力の時の表面張力はこのような式で表すことができる。
表面張力 γtotal = γd + γp + γdHacid + γdHbase
HSPの4列にHSPファミリーのどのような値を入れるかは研究者の好みである。
接着とかを扱いたいのであればdHacid, dHbaseやElectron Donor, Electron Acceptorに分けるのが合理的だ。各HSPの後ろには表面張力に関係しそうな項目をY-MBの中から選ぶ。例えば表面張力は温度や圧力が高くなると小さくなる物性なので、1-Trや1-Prの形で入れてあげると良いことが多い。金魚のフンの項目は4つで同じだが、求まった指数の部分は各HSPごとに異なる。必要な臨界温度(Tc), 臨界圧力(Pc), 分子体積(MVol), 球形度(Ovality)はY-MB Pro(pirika.com社製物性推算ソフト)でSMILESから計算することができる。炭素材料の接着の部分で使い方の解説を行った。
これを単純にHSPの値だけで表現している式もあるが、トータルが合わないし、温度依存性も計算できない。
任意の温度での液体表面張力を成分ごとに計算
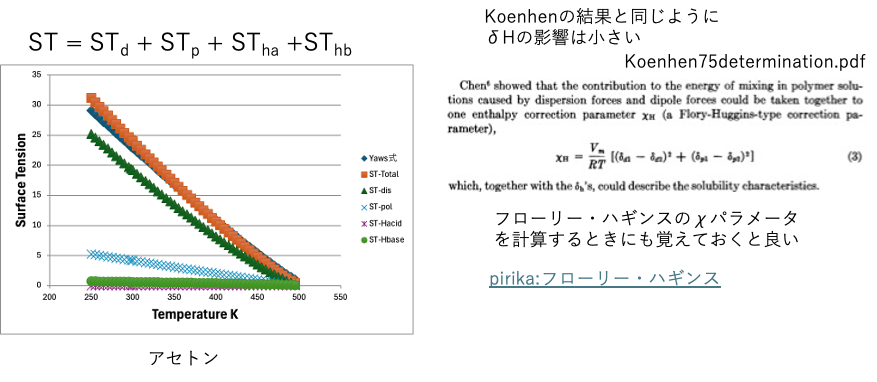
HSP-MIRAIで式が求まっているので、各成分が温度を変えるとどう値が変わるか計算で出すことができるようになる。
ポリマーγcの分割

ポリマーであってもHSP-MIRAI法で臨界表面張力を分割することができる。ただしポリマーの臨界界面張力やユニット体積、ポリマー骨格のメインの部分、側鎖の部分の体積比、温度の効果としてポリマーのガラス転移温度が必要になる。これらはY-PB Pro(pirika.com社製ポリマー物性推算ソフト)でポリマーSMILESから計算することができる。炭素材料の接着の部分で使い方の解説を行った。
まとめ
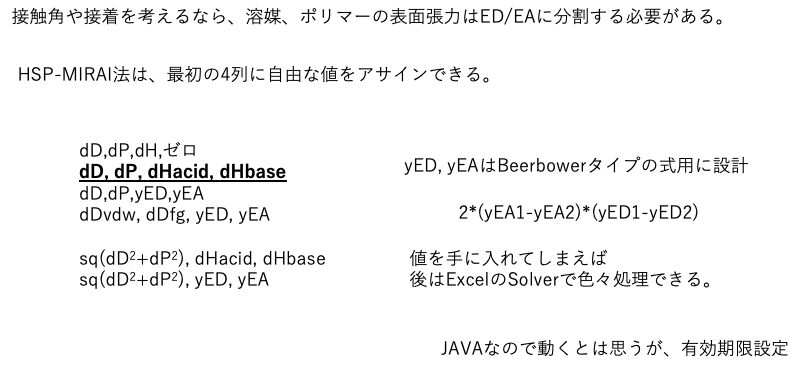
HSP-MIRAI法のプログラムはJAVAで作ったアプリケーションなので、マシンを選ばず動作は可能だ。ただし決定しなくてはならない係数はとても多いので、それなりのスピードのマシンで動作させる必要がある。
コンサル対象には提供を始めている。

「AIよ。HSP-MIRAI法は熱物性値をHSPの定義、分散項、分極項、水素結合項などに分割する技術だ。」への1件のフィードバック
コメントは受け付けていません。